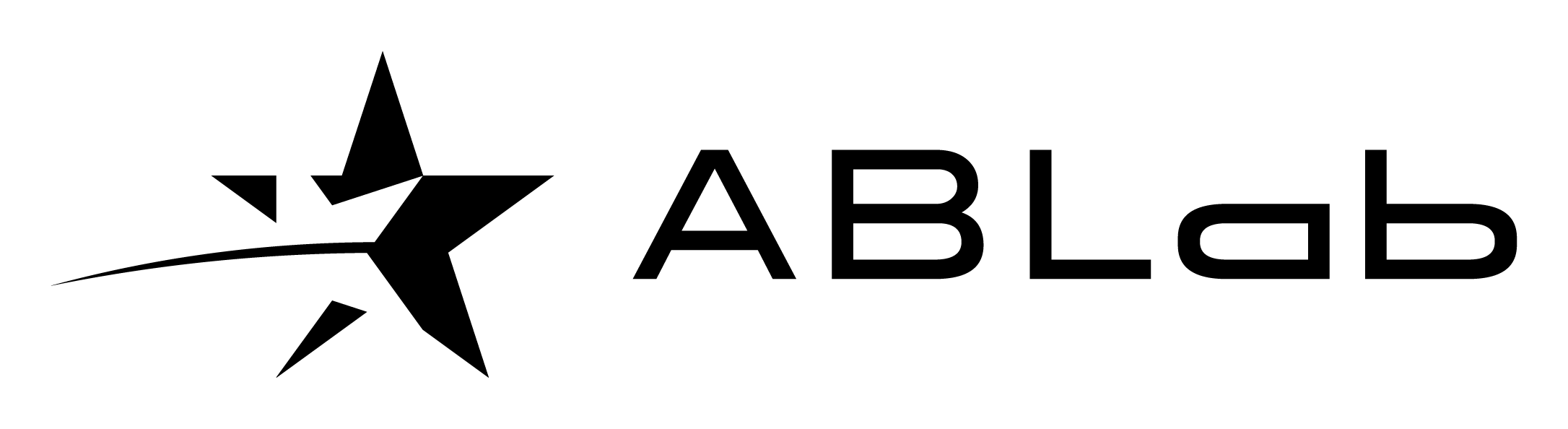山崎直子氏ら宇宙識者が語る「宇宙開発利用の拡大に向けた展望 ~宇宙開発利用大賞から得られた気付き~」

ABLabの伊藤です。第3回宇宙開発利用大賞の選考委員によるパネルディスカッションの模様をレポートします。テーマは「宇宙開発利用の拡大に向けた展望 ~宇宙開発利用大賞から得られた気付き~」。今後の宇宙利用を考える上でのヒントもあるかもしれません。
|
テーマ:「宇宙開発利用の拡大に向けた展望 ~宇宙開発利用大賞から得られた気付き~」 <パネリスト(第3回宇宙開発利用大賞 選考委員)> <モデレーター(第3回宇宙開発利用大賞 選考委員長)> |

柴崎 亮介 氏(東京大学 空間情報科学研究センター 教授)
受賞事例についてのコメント
各受賞事例について、審査員各位からコメントをいくつか抜粋してご紹介します。
遠藤氏
どれも素晴らしく迷った。もっとも注目したのはアクセルスペースの取り組み。ベンチャーが日本でなかなか出てきづらい中の取り組み。小型衛星において、実績があり、利用を進めている。ますます成長していくはずなので、そのインパクトなどに期待している。
神武氏
マゼラン社の衛星測位。人の生活に貢献するかちを生み出すというのが重要。九州大学は、国連とも連携した留学生事業。宇宙システムは大事な外交手段になる。人材が育たないといけない。日本を好きになってもらわないといけない。世界における日本の立ち位置を高める。
土田氏
今回受賞しなかった事例の中にも素晴らしいものがたくさんあった。これは次回は受賞になりそうだなという事例も多かった。
このイベント「宇宙開発利用大賞」をどう利用していけば良いか

遠藤 典子 氏(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授)
遠藤氏
継続と発展が重要。これからIoT時代になると、宇宙だけでなく地上との競争も生まれる。なぜ宇宙でないといけないのかが問われ始める。エコシステムを整えていくのが政策の役割。

神武 直彦 氏(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授)
神武氏
できるだけ他分野の方と取り組むのが重要。審査としては、誰のためのサービスなのかが明確に書かれている提案はインパクトがあり響きやすい。ぜひ、他分野の人と取り組んで提案して欲しい。

篠原 ともえ 氏(アーティスト・デザイナー)
篠原氏
ファッションと宇宙のコラボに期待している。受賞には至らなかったが、宇宙の写真をファッションに取り入れるという事例も素晴らしかった。200近い応募のうち、エンターテイメント分野がなかったので今後に期待したい。
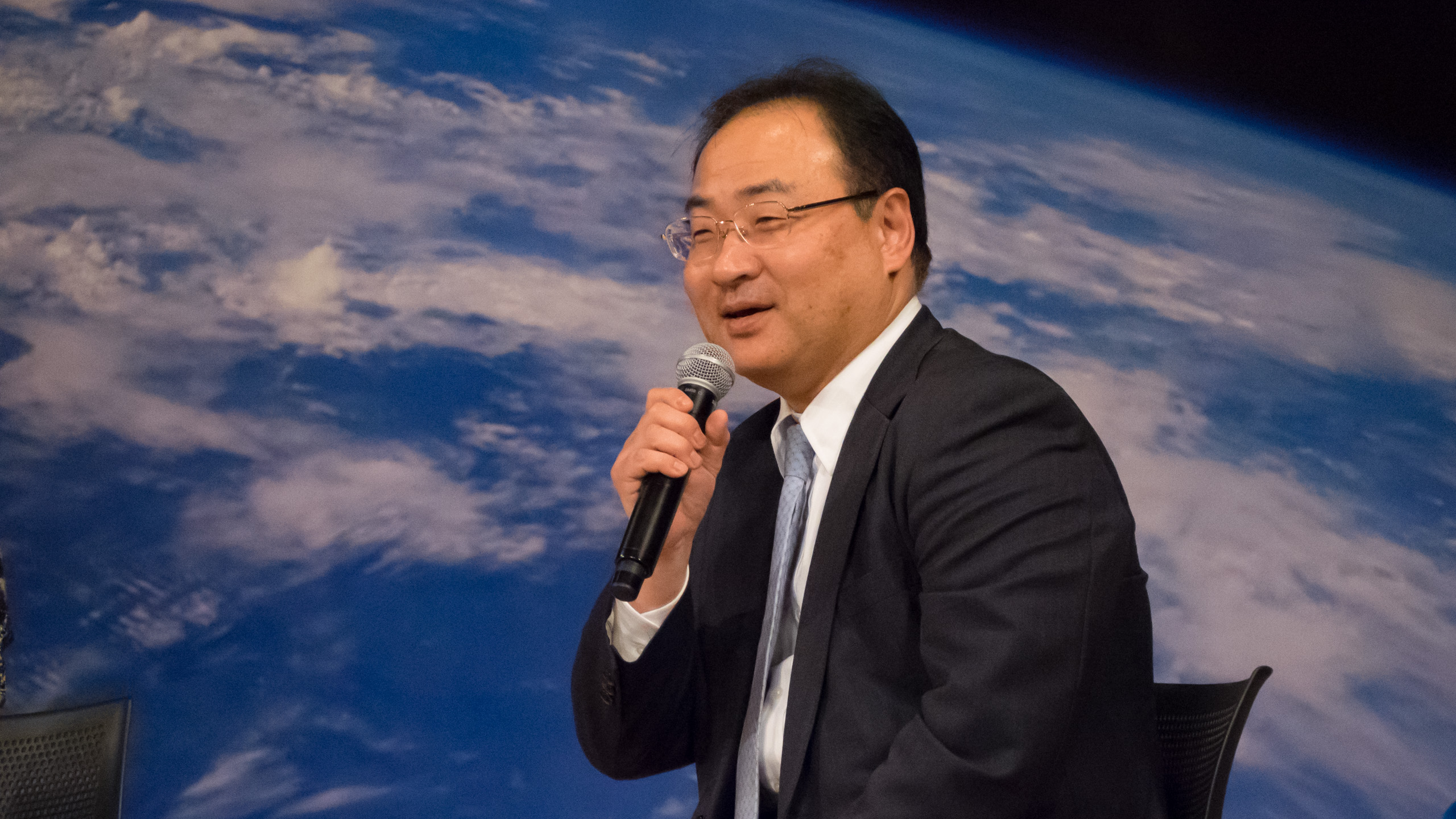
土田 誠行 氏(株式会社 産業革新機構 専務取締役)
土田氏
宇宙産業が情報産業へとステージが変わってきた。私は周囲に、宇宙は儲かると言い切っている。なぜ宇宙なのか、宇宙だからこそというのをアイデアに取り込んでもらえると、グローバル展開しやすいのではないか。
宇宙データをオープンにし利活用を推進していきたい。宇宙データでどんな面白いことができるのか、今後どんどん出てくると思う。掛け算が大事。宇宙との掛け算をしてほしい。キーワードは、掛け算、グローバル、異業種。

山崎 直子 氏(宇宙飛行士)
山崎氏
課題解決、ソリューションに移行してきている。誰のための、そういうのを示すと賛同者も増える。相談窓口も充実してきているので、窓口を活用して、ネットワークの力を利用して欲しい。
柴崎氏
宇宙のスケーラビリティをうまく使って欲しい。これまでの3回では国内の事例が多かった。これからはグローバルな観点で。
まとめ
以上、内閣府主催宇宙シンポジウムでのパネルディスカッションの内容をお届けしました。
内閣府主催宇宙シンポジウムの全体レポートは以下の記事をご覧ください。
https://ablab.space/event/uchuriyo-simposium-2018/
投稿者プロフィール

- 代表理事
- 1983年、福島県生まれ。IT業界で約10年マーケティングの経験を積んだ後、ファンブック株式会社を設立し独立。2018年、当時小学1年生の息子と宇宙の勉強を始めたことがきっかけで、宇宙ビジネスの潮流を知り、半年後に宇宙ビジネスコミュニティ「ABLab」を創設。「地球上のすべての業界を、宇宙産業に巻き込む」というビジョンを掲げ、異業種から宇宙に挑戦する人や企業を支援し、事業創出と人材輩出に取り組む。
最新の投稿
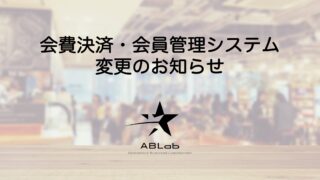 お知らせ2024年7月20日ABLabの会費決済・会員管理システムを「会費ペイ」に変更します
お知らせ2024年7月20日ABLabの会費決済・会員管理システムを「会費ペイ」に変更します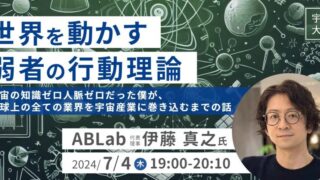 お知らせ2024年6月21日【7/4】宇宙産業機構が運営する宇宙大学にて、ABLab代表の伊藤が講演します
お知らせ2024年6月21日【7/4】宇宙産業機構が運営する宇宙大学にて、ABLab代表の伊藤が講演します お知らせ2024年3月21日ABLab、宇宙ビジネスの展示会 SPEXA 出展のお知らせ(来場者登録無料)
お知らせ2024年3月21日ABLab、宇宙ビジネスの展示会 SPEXA 出展のお知らせ(来場者登録無料) イベントレポート2024年3月6日2024 国際宇宙産業展 ISIEX のABLabブース出展レポート
イベントレポート2024年3月6日2024 国際宇宙産業展 ISIEX のABLabブース出展レポート